私は保守ではない。保守はイデオロギーを警戒して、慎重に接することを基本とする立場とされているからだ。私は民族主義者である。そのため保守というよりも急進右派と自称した方が適切だろう。そんな民族主義者にとって本書は教科書と言えるような一冊である。私の考える「民族」とは、本書でいうところの「エスニシティ」に近い概念で、言語や文化よりも血統を重視する。
本書でも述べられているとおり、エスニシティで重視される血縁とは、実際にあるかどうかよりも、血縁がつながっているという漠然とした感覚が重要であるとされる。最新の医学研究によると、人間は先天的な遺伝子だけでなく、後天的にもエピジェネティックに遺伝子のオンとオフが変化するという。ウイルスが人の遺伝子を変異させるという学説もあるが、火山の噴火も強力な大地の氣を放出し、エピジェネティックな刻印をヒトに残す。そのため私は、世界最高の霊峰である富士の三大噴火をすべて経験した祖先を持つ者を日本民族と定義することとしている。延暦大噴火は800から802年、貞観大噴火は864から866年、宝永大噴火は1707年にあったと伝えられているので遅くとも8世紀くらいまでに日本列島に祖先がいた人だけが日本民族ということになる。証明できるものは近代以降の戸籍しかないので、戸籍上古くから先祖が日本にいれば日本民族だと漠然とした感覚でよいだろう。こうしたゆるやかさが同族意識には大切なのである。
ナショナリズムの四類型は現在の世界の民族問題を参照する上でも有益である。日本は民族の分布範囲と国家の領土がほぼ重なっている、本書にて三つ目に挙げられているナショナリズムの型に該当する。そのためナショナリズムはすでに達成されていることもあってナショナリズムが不活発だったが、グローバリズムにより国民国家が侵害されかけていることによって強力なナショナリズムが目覚めつつあり、いち早く目覚めた者はいまだ民族的一体性を自覚していない者を目覚めさせようとするとの説明のとおりになっているように見受けられる。
ナショナリズムは外集団に対しては政治的につくられたものだとし、内集団については自然なものと多くの人が考えがちだという点も正鵠を射ていると思う。ただし日本民族のナショナリズムだけは絶対的で自然なものであると私が確信しているくらいには。
ソヴィエト政権に人為的に設定された中央アジアの諸民族は、数十年間分割して統治された結果、それぞれの国に支配者層ができてしまい、統一国家をつくる機運がなくなったという指摘は興味深かった。民族の定義は他者の策謀によってではなく、自分たちが自然に感じられる形で設定しなければならないという教訓になる事例である。
著者は歴史論争が招くナショナリズムのぶつかり合いは対立を亢進させるとしているが、逆に各国の主流派民族同士の世界同盟によりお互いの主権を尊重し、ナショナリズムを保全し合うという形の世界秩序もあるのではないか。すべての少数民族に民族自決を認めては際限のない民族国家の分立が起こってしまうので、零細民族には国家建設を認められないこともある。多様性として認められるには、一定規模の民族的普遍性が必要なのだ。それならば現在の世界における少数派の際限ない要求も却下されてしかるべきものは多くある。一度、冷静になって整理する必要があるだろう。
日本でも1950年代までは左翼陣営が盛んに愛国、ナショナリズムを唱えていたらしい。確かに古い映画を観たり、古い書籍を読んだりしていると、現在の国賊左翼とは似ても似つかないような愛国的言動の左翼が描かれていることがあり、私も違和感を抱いたことが何度かあった。そういう人も中にはいたのだろうと軽く受け流していたが、昔は左翼にも立派な人がいたのだなと少しだけ見直した。今日の恥ずかしいサヨカルたちにもリベラル・ナショナリズムの作法を少しは学んでほしいものである。学べるだけの知能と品格があれば、の話だが。
著者の述べるとおり、人間は純粋な個人ではない以上、「普遍的人間」として生きることは不可能であって、集団帰属意識は生きる上で必須である。そして帰属対象はナショナリズムに根ざしたものでなければならない。民族という帰属対象は、怪しげなイデオロギーなどとは一線を画するきわめて安全かつ信頼できる帰属対象だと言える。
資源(富、権力、名誉など)が希少になったとき、集団的対立は紛争に発展しやすくなるという指摘もある。裏を返せば、今の私たち日本人は、資源が希少になっているにも関わらず結束して闘えていないがゆえに権益を外国勢力に奪われ続けているとも言える。民族的団結が妨げられていることが私たちの弱点である。それはつまり、改善できれば大きく飛躍に転じることができる要素ということでもある。日本人の大きな伸びしろは、民族主義にこそある。私は、それを促進する組織集団を整備したいのである。

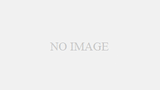
コメント