日本民族の信仰活動が不活発なのは、保守的な宗教がないからである。諸外国の主流宗教を見ても信仰に厚い人は変化を警戒し、帰属意識を強めるために宗教を求めているとわかる。宗教というのは保守的でなければならず、先行きが不透明で人々が不安を感じている世の中にあっては保守的でない宗教など信仰者の精神の安定につながらないので無価値なのである。大衆に迎合するのであれば宗教である必要がない。革新思想の宗教など存在するに値しない。
そもそも日本人をはじめとするアジア人は不安を感じやすいセロトニントランスポーター遺伝子S型の人が多いとされているので、他人種のような劇的な改革はそもそもしてはいけないのである。社会はたった一つしかない大切なものなのだから、訳のわからない左翼思想の実験場にしてはならないのである。
とはいえ変化は自然の摂理なので、現状維持を志向する保守派よりも、現状変更を志向する革新派の方が勢いが出がちなのは事実である。その構図では自分の失点を減らすことが目標の保守と、自分の得点を増やすことが目標の革新という形になってしまい、保守にとってはいいことが一つもない。ゆえに血盟も結束して望ましい変化を求めていくべきである。その結果として互いに別方向への変化を求め合うことで、結果的に現状が維持されることも考えられる。変化が自然の定めなのであれば、望ましい変化を私たちも求めていかなければ損である。
そうして改革を進めていくにあたって、私はエドマンド・バークの保守主義に倣って、少しずつ改善を重ねていく漸変主義をとる。中間団体の強みを活かして全員の意見をよく聞いて上へと吸い上げていく仕組みをつくり、その上で慎重に改革するが、もしもうまく行かなかった場合はただちに元に戻すようにする。それでこそ気負わずに改革に挑めるようになる。革新派のような無責任な一方通行の改革はしない。
政治が大きな権力によって改革すると、ほとんどの場合失敗する。人間のちっぽけな理性ごときでは複雑な社会のことなど完全にはわからないのだ。それにもかかわらず傲慢にも、こうすればよくなるなどと無責任に主張して改革を一方通行で進めるのは乱暴である。一例を挙げると人体を理解しきったつもりになって盲腸を不要扱いして切除してきたが、重要な役割があることが後にわかって問題となった医学界のようなものだ。社会の改革も一方通行で進めるのではなく仮説を立てて変更内容の同意を得たら、期間と評価方法を事前に設定した上で小幅に改革を試行していくようにすべきだ。強い中間団体として、私たちが圏内で試行錯誤して漸変主義を実践、普及させていきたい。間違いに間違いを重ねて振り返らない革新主義は、社会との根本的な向き合い方からして不適切である。
改革には反発がつきものだが、反発は集団の団結を乱す。一定期間試しにやってみて、その結果と照らし合わせて修正しようとする漸変主義でこそ反発をなだめて試行していける。
また宗教集団は変化がゆるやかなので、世の中の変化について行けない人たちのための居場所も担保する。変化を強いられない自由、押し付けられた変化を拒否する権利を宗教は保障する。変化しない根本の伝統、慣習があってこそ一時的な流行や風潮など詮無いものに踊らされることなく、世代の違いを越えて団結できる。その安定感が共同体を強く保つ。人は集まると強く、散ると弱い。血と掟は血盟を結び付けて強くしてくれる。
どこの国でも保守は常に主流派である。その保守派の願いに沿う形で改革は実行されるべきである。分けても日本人は保守的な民族である。保守派の強みである集団性は、当然だが集団でないと発揮されない。日本人の強みが発揮できる温かい集団に基づく体制を整えて日本を復活させよう。

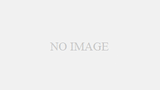
コメント